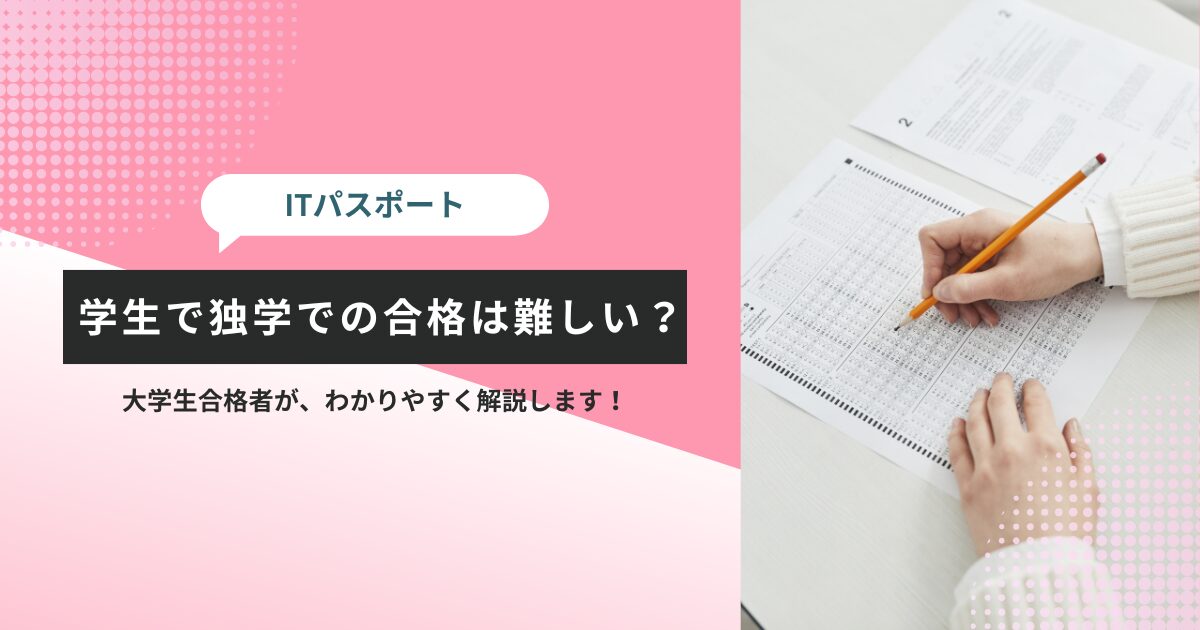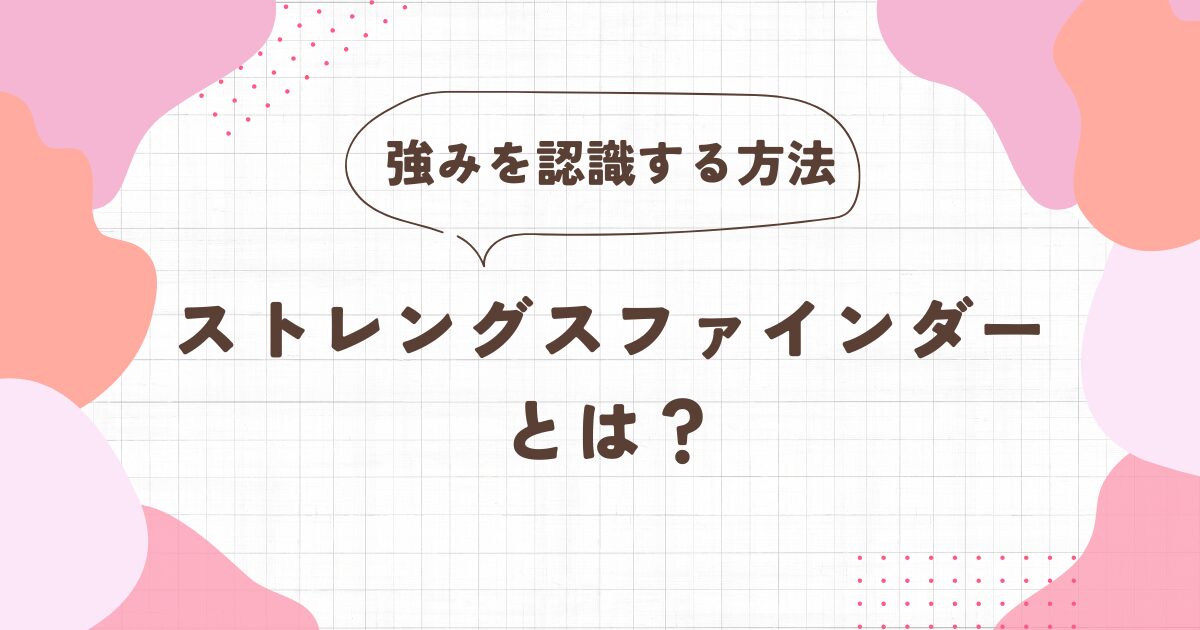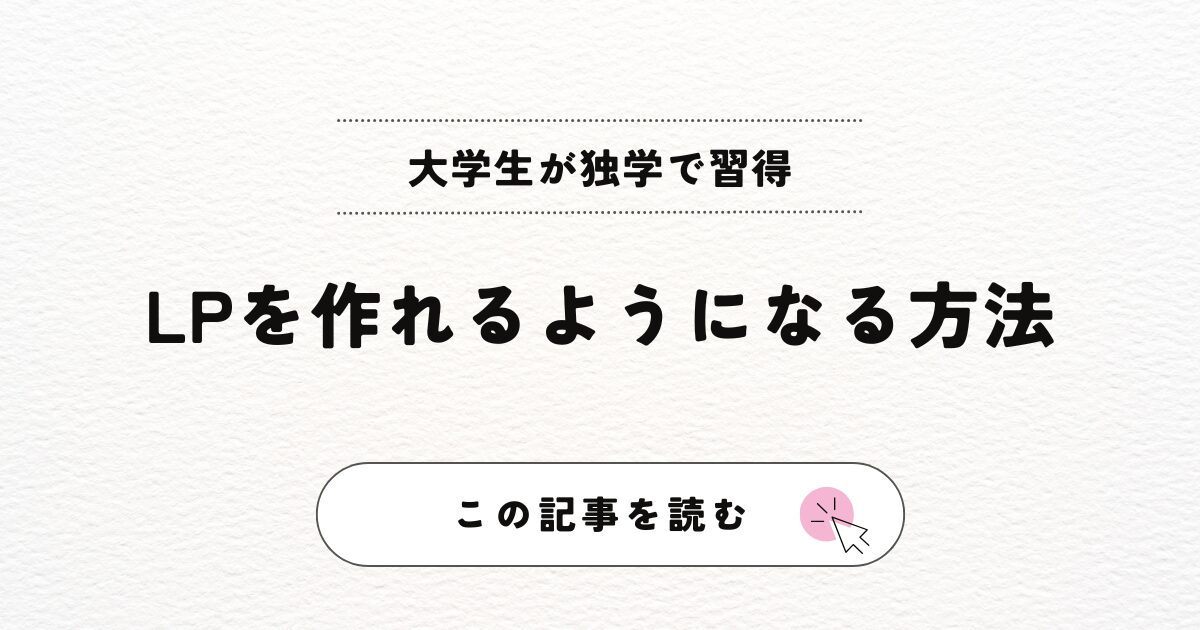おすすめのメモの取り方【あなたにとってわかりやすく書く】
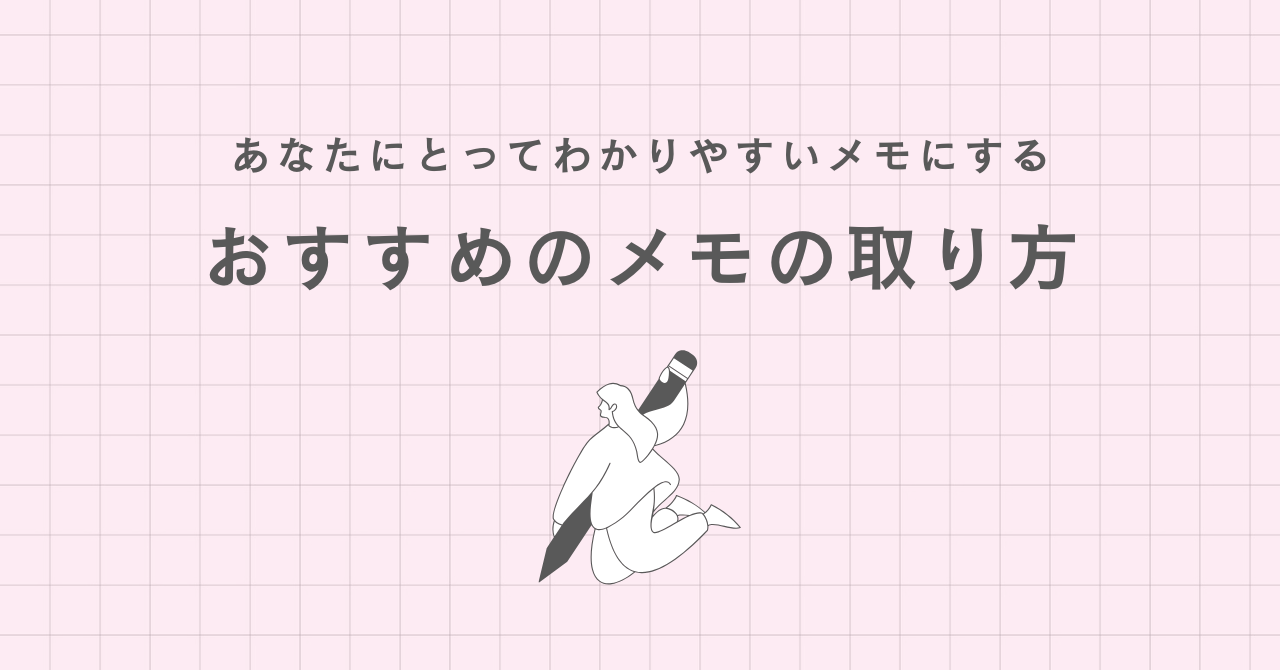
こんにちは!
なのかです!
授業やセミナーなどを受けていて、「うまくメモが取れない」「メモを取っても、そこで終わってしまう」と感じた経験はありませんか?
メモをとるときは理解することを意識したメモの取り方や見返したときにためになる取り方をすることで、メモの効果を最大限受けることができます。
私が過去にメモの書き方を迷っていたときは、「どのようにメモを取ればいいのかわからない」「メモを取ってもあまり意味をなさない」「きれいに書くことを意識しよう」と思っていました。
しかし、メモの取り方を意識することで、何度も見返すメモになりました。
今回はこのような悩みを私の実体験を活かして、効果的なメモの取り方📝を解説します。
これから授業やセミナーを受ける際に、ぜひ参考にしていただけますと幸いです✨
メモをとる目的
記事の内容に入る前に、メモを取る目的についてお伝えします。
メモを取る目的は以下の3つがあると考えています。
- 内容を理解するため
- 忘れないようにするため
- あとで見返したときすぐに思い出すため
①内容を理解するため
1つ目は、聴いた内容を理解するためです。
話を聴く場合、自分がはじめから完璧に理解していることである可能性は高くはないと思います。
そのため、まずは内容を理解する必要があります。
聴いただけで理解できるものもありますが、理解したつもりになっているものもあります。
メモを取る際に自分の言葉で改めてまとめることによって、頭で考えて、文脈や内容を理解して、メモに起こすため、わかっていない部分を自覚することができます。
話を聞く=インプットしながら、メモをとる=アウトプットをすることで、理解を進めましょう。
②忘れないようにするため
2つ目は、聴いた内容を忘れないようにするためです。
聴いた内容を「聴いた」だけで終わらせてはいけません。
その聴いた内容の中でも特に大事だと感じた部分や今後に活かしたいと思ったところを書き留めておくことで、忘れにくくなります。
③あとで見返したときすぐに思い出すため
3つ目は、あとで見返したときすぐに思い出すためです。
友達や家族と話しているときに出てきた単語や話題をそれ以前に授業やセミナーなどで聞いたことがあるけど、思い出せない……なんてことありませんか?
そのときに、どんな内容だったかが書き留められていると、振り返って、内容を再度インプットすることができます。
聴いたその瞬間に役立つだけでなく、その後にも役立てることができます。
効果的なメモの取り方のコツ
では、メモを取る目的がわかったところで、実際にどのようにメモを取るとよいのかをご紹介します!
ここでは、「効果的なメモの取り方のコツ」について説明します。
まず、前提の「メモを取る」ということですが、聴いたことをまとめるということにつきます。
聴いたことをまとめるという文字だけ見たら、簡単そうに見えますが、ただ聴いたことをそのまま書くのではありません。
それでは、効果的なメモの取り方のコツですが、以下のつです。
- きれいにまとめず、丁寧にまとめる
- 文字だけにしない、線や図を使う
- 手書きにする
これは私が大事にしていることでもあるので、人によって合う合わないがあるかもしれません。自分にとっても効果的だと思うものを取り入れてみたらいいと思います。
➊きれいにまとめず、丁寧にまとめる
きれいにまとめないってどういうこと?きれいにまとめると丁寧にまとめるは何が違うの?とはてなを浮かべたと思いますが、どういうことかはここから説明しますね。
みなさん、メモを取ったり、ノートをまとめるときは、文字の配列の美しさを求めたり、きれいな色を使ったり、何色ものペンを使って書くことに意識を働かせて、きれいにまとめようとなりがちです。このときは、内容に身が入っていないことが多いです。
きれいにまとめることが大事なのではなくて、丁寧にまとめることが重要です
丁寧にまとめるということは、自分が見て、内容が分かりやすくなるように書くことです
❷文字だけにしない、線や図を使う
文字だけだと、視覚的な理解が十分ではありません。
そのため、文字を書くだけでなく、内容につながりがあるところは線でつなぐ、話の内容をわかりやすい図で示すことができそうであれば、図を使って表すと理解が進みやすくなります。
また、自分なりのルールを作るとよいと思います。もちろん、じゃあルールを作って、頑張ってねと丸投げはしないので、安心してくださいね。
ここからは、私がよく使うものをルール付きで紹介します。
矢印
矢印は、こことここにつながりがあるよと自分があとで見返したときにわかりやすくしたり、バラバラに話されたことがのちに自分の中でつながったと解釈できたことを示すときに役立ちます。
下線
下線は、目立たせるときに使います。私の場合は基本的に文字を書くときに文字の色を変えることはせず、すべて同じ色で書くので、下線を引くことで特に重要なところを目立たせる役割をしています。
記号
記号は、別々の場所に書いてしまったけど、つながっているところや関連のあるところに同じ記号を書くようにしています。
また、その話の1番重要なところであったり、まとめになるところに★マークをつけています。
数字
数字は、手順やフローがある場合にその順番がわかるように①②のように番号を振ります。
また、もし同じページで数字が2回以上出てきたときには同じ形式にならないように、とのように違いがわかるように区別させています。
囲い
囲いは、注目させたい部分や大事にしたい部分を楕円や四角の枠で囲います。下線と違い、文章すべてのときに使っています。
❸手書きにする
これはメモを取る目的から棚卸した結果、手書きにすることが1番よいと私は考えています。
上記で示した、メモを取る目的は覚えていますか?
- 内容を理解するため
- 忘れないようにするため
- あとで見返したときすぐに思い出すため
結局は、内容を理解し、忘れないように書き留めておくことが目的になります。
手書きでない場合は、パソコンやスマホに打ち込むことを想定しています。パソコンを使うと、タイピングを早くすることができれば、聴いた内容を全て文字起こしすることができます。もちろん文字起こしをすることも振り返りでは使うことができますが、そのときの内容理解には向いていません。
特に、私はパソコンで打つと耳の右から左に内容が抜けていく感じがして、全然覚えられませんでした。
これに対して、手書きの場合はすべてを文字起こしして書くことは難しいです。
必然的に内容をまとめて、書かなければならなくなります。その過程で内容を理解して、わかりやすくまとめるということができている状態になります。
そのため、内容を理解する・忘れないようにするという観点から、手書きをおすすめします。
メモをするために使うもの
ここでは、実際にメモを取るときに使っているものをご紹介します。
私が使っているのは以下の4つです。(かっこの2つは使うときと使わないときがあるものです)
- 無地のリングノート
- 黒のボールペン
- (赤のボールペン)
- (蛍光ペン)
無地のリングノートは、ダイソーに売っているリングノートを使うことが多いです。
ここで大事なポイントが無地・ノートを使うことです。
まず、無地のものを使う理由は、罫線に縛られず書くためです。
罫線があると、無意識に文字の大きさを線に合わせたり、図が小さくなってしまう場合があります。効果的なメモの取り方のコツの➊で書いたように、きれいに書くことは重要ではありません。そのため、あえて線のない、無地のものを使うことをおすすめします。
次に、ノートを使う理由は、メモがどこかにいってしまわないようにするためです。
これは容易に想像がつくと思いますが、ルーズリーフなど、1枚ごとにバラバラのものを使うと、途中で差し込みができるというメリットはありますが、1枚だけどこかに行ってしまったりと管理が難しいというデメリットがあります。今回のメモは後で見返すということも想定しているので、バラバラでどこかへ行ってしまうことは避けたいところ。
私がよく使っているのはダイソーに売っているリングノートです。
黒のボールペンは、どんなものでもよいですが、個人的にはJETSTREAMのボールペンがおすすめです。様々なボールペンを使ってきましたが、メモのときにはスピーディーに書けるか、文字がつぶれにくいかということが比較項目になると思っていますが、JETSTREAMが1番よかったです。
また、赤ボールペンや蛍光ペンは、下線を引くとき、図を書くときに違う色にしたい際に使用します。
まずは自分にとってわかりやすく書くことを意識しよう!
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました!
この記事の中でも何度かお伝えしていますが、自分にとってわかりやすく書くことが大事です。
私は几帳面なタイプなので、昔はきれいな字を書くことばかりに意識を向けてしまっていましたが、このメモの取り方をしてから、理解のしやすさも上がったと思います。
何度かやっていると、自分なりの書き方のルールやこうした方が内容の理解が深まりやすいというものも見えてくると思います。
この記事が、あなたがメモを取る際に少しでもお役立ていただければ、嬉しいです。