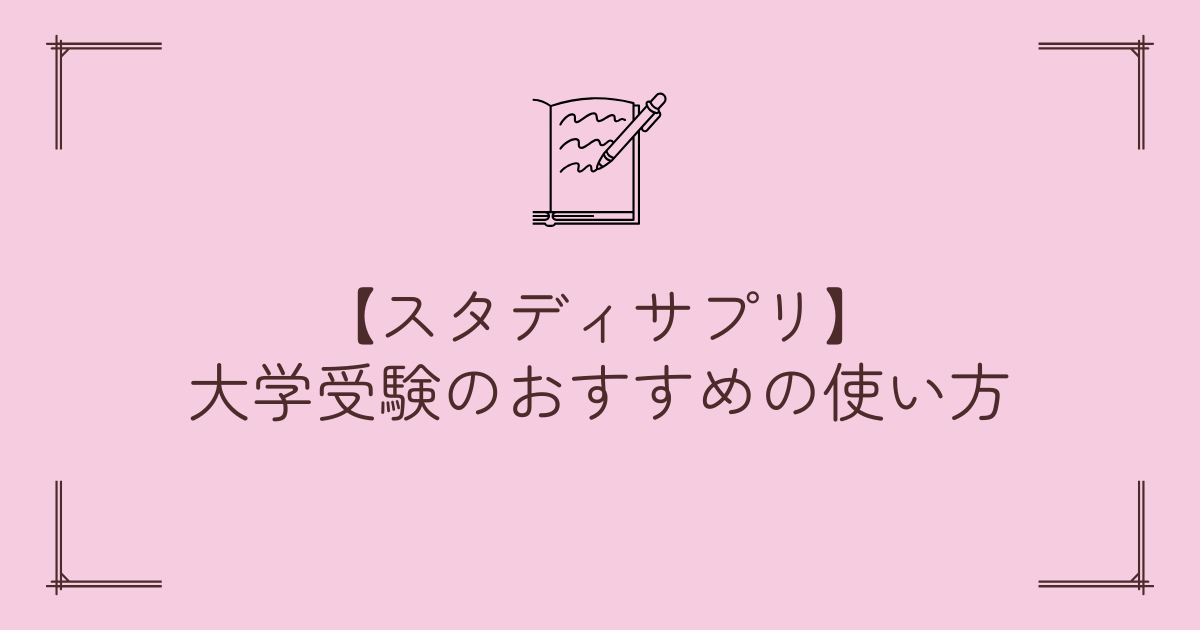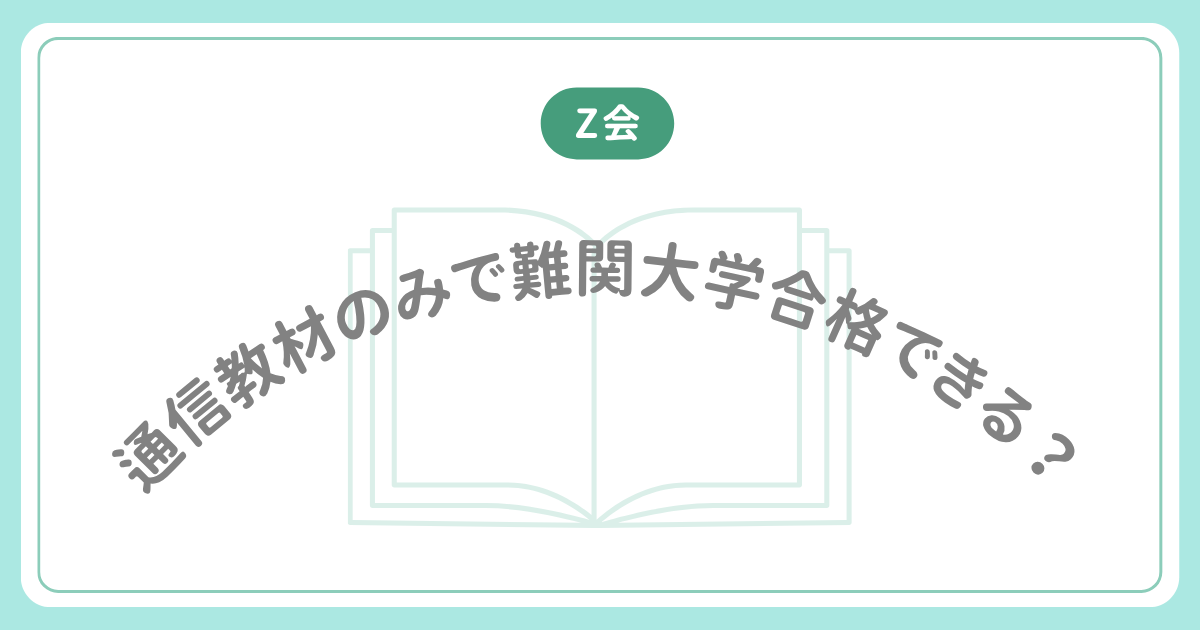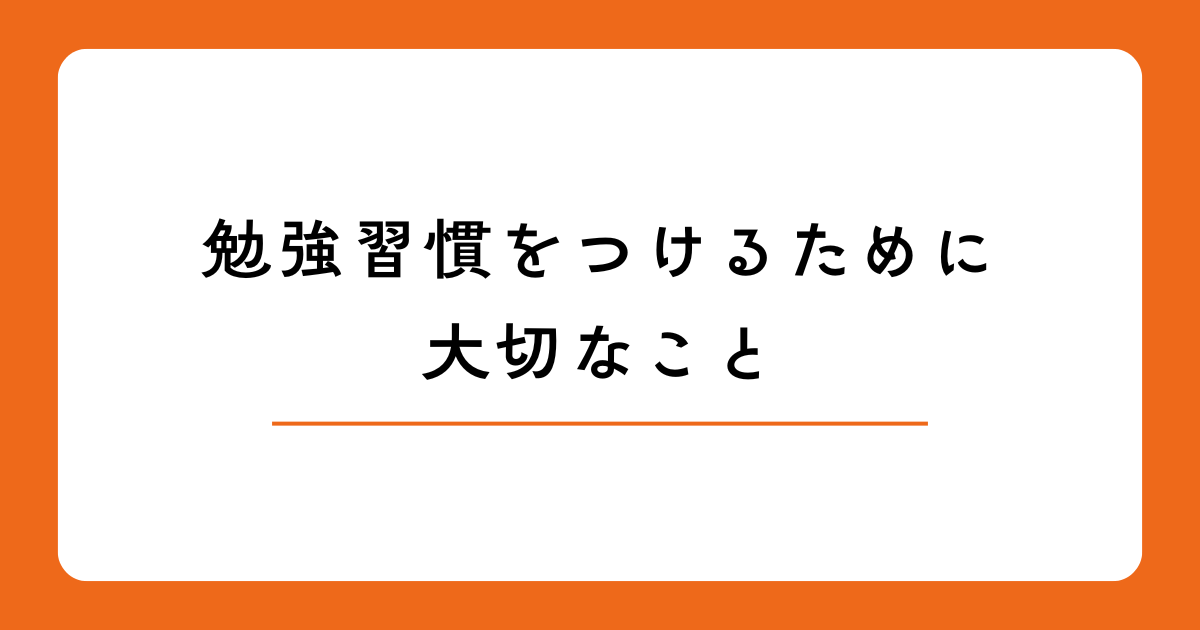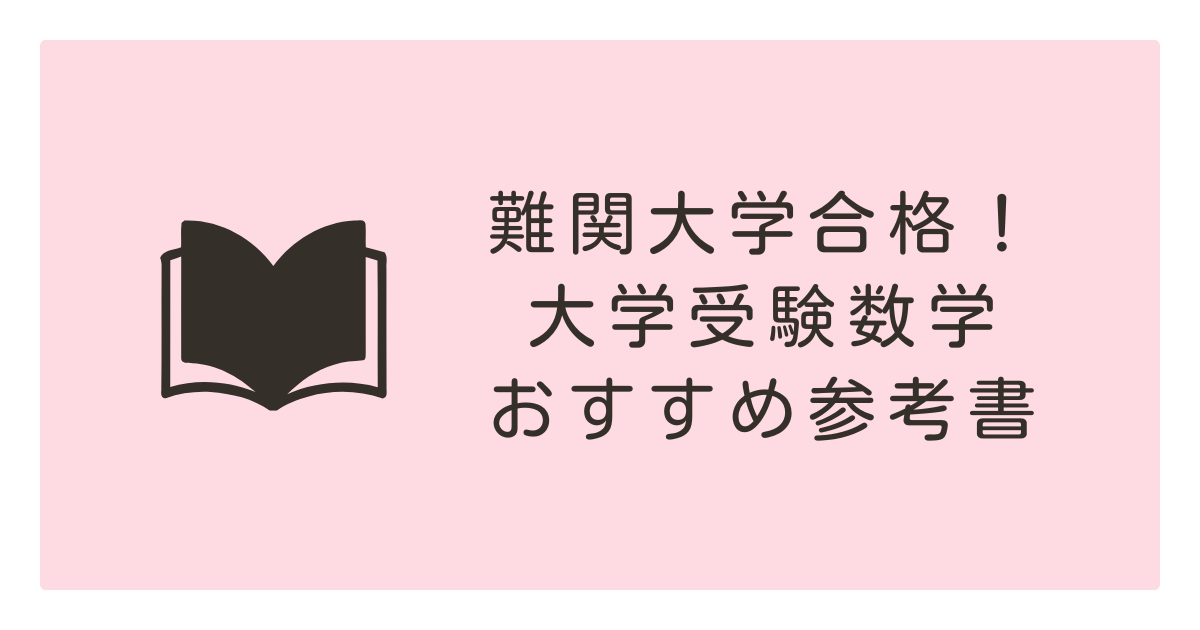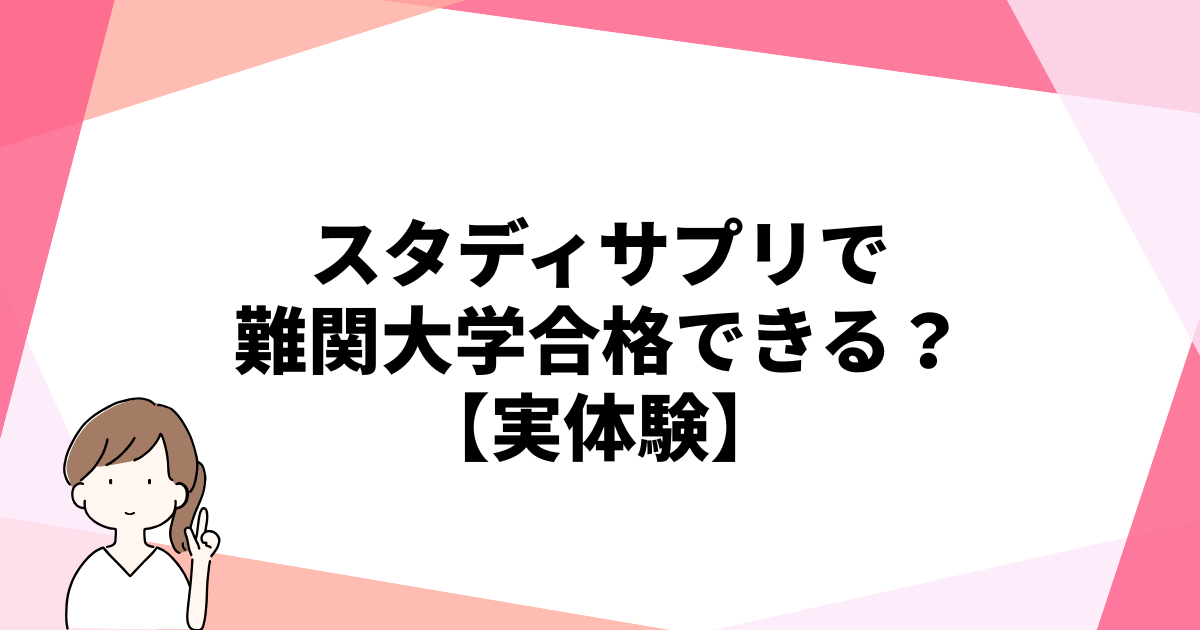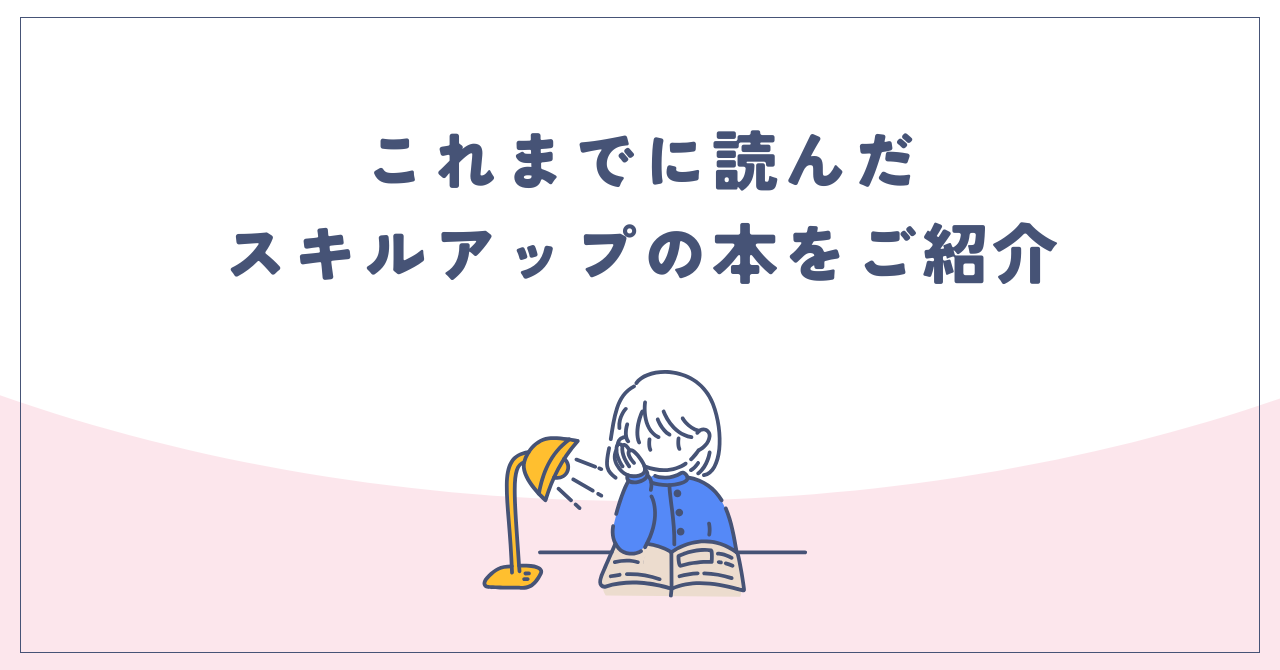資格取得に向けた勉強方法【実体験でおすすめします】
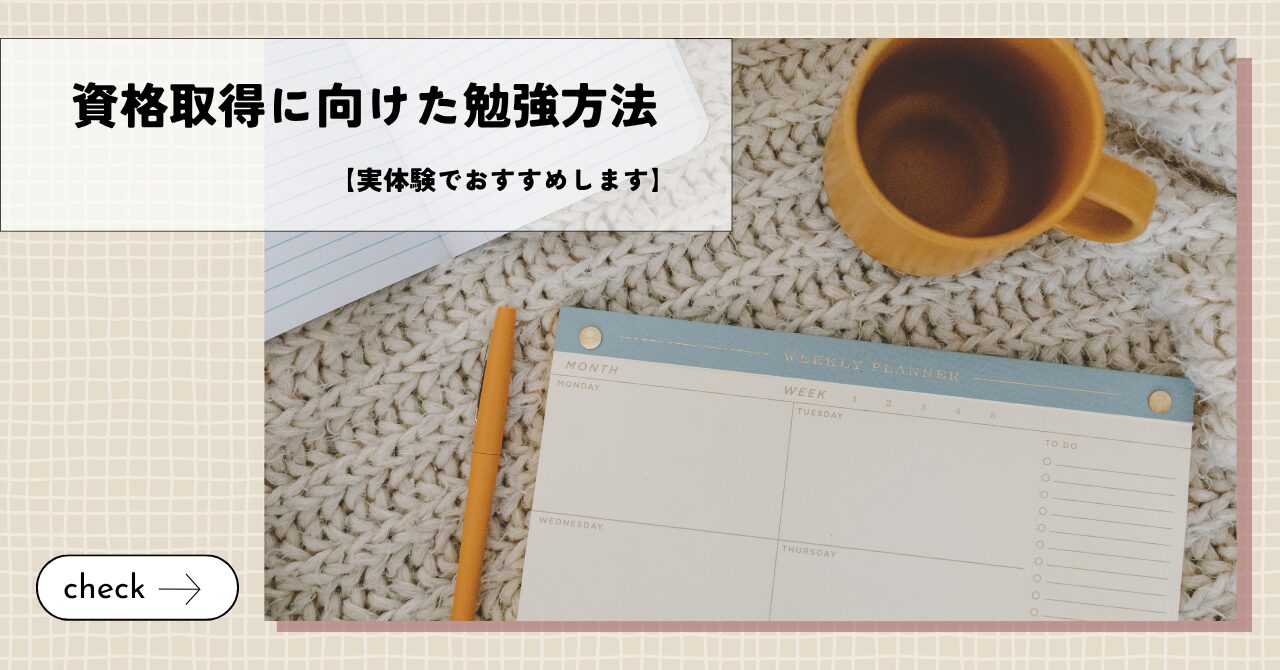
資格を取ろうと思っているが、「勉強はどう進めたらいいのか?」、「参考書はどう選んだらいいのか迷う」と思ったことがあるのではないでしょうか?
これまでに、TOEFLやITパスポート、英検など、いくつかの資格取得に向けて、勉強してきました。ITパスポートは大学生になってから、勉強し、合格しました。その他にも試験は受けていないですが、勉強を進めたものなどがあります。
過去に私が資格の勉強を始めようと思ったときには進め方に迷い、様々なサイトや体験記を見てきました。
この記事では、これまでの経験をもとに資格取得に向けた勉強方法について、紹介します。特に大学生は学校の勉強や就活と同時に行っていると思うので、時間の使い方についてもご紹介していきます。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです📝
勉強に入る前段階
まず、勉強に入る前段階について解説します。
勉強を始めるまでには、以下の4つが必要だと考えています。
- 資格取得の目的を考える
- 試験の概要を調べる
- 試験日を決める
- 参考書や問題集の購入
資格取得の目的を考える
1つ目は資格の目的を考えることです。
例えば、
- 専門知識を持っておくため
- 大学の単位をとるため
- 就活に役立てるため
- 興味がある分野で知見を深めるため
などです。
目的を持つことで勉強に対するモチベーションが下がったときに、モチベーションを高めることができます。
目的を考えるときには、自分がなぜ資格を取るのか、資格を取りたいと思った理由から考えましょう。
そして、その目的を含めて資格取得を宣言したり、目標として見えるところに書いておくことをおすすめします。ひとりで頑張るというのは難しいときもありますが、周りに伝えたり、自分の当初の想いを言語化しておくことで、再度頑張ろうと奮起することにつながります。
私は、家族に「〇〇の資格を△△のためにとる」と伝えていました。
試験の概要を調べる
2つ目は試験の概要を調べることです。
私は以下の5つは必ず調べます。
- 試験日はいつごろか
- 範囲はどこか
- 試験時間はどれほどか
- 点数配分はどれほどか
- どの程度の点数を取れば合格できるのか
試験の概要がわかってはじめて、勉強を始めることができます。
概要を調べ、資格を取得するためのゴールを明確化しましょう。
試験日を決める
3つ目は試験日を決めることです。
先に試験日を決めて、申込まで済ませておくと、なお良いですね😄
申込をすることで、そこまでの日数で集中して勉強に取り組むことができます。資格は受験や学校のテストとは違って、この日に受けなければならないという日が決まっているわけではありません。自分で決める必要があります。試験日を先に伸ばすことはできるので、先に決めて、ゴールから逆算できるようにするのが良いと思います。
参考書や問題集の購入
4つ目は参考書や問題集の購入です。
資格は基本的に参考書をもとに勉強を進めます。資格範囲の内容が網羅されている参考書がいくつかあるので、自分に合ったものを選びましょう。
私の場合、参考書の選び方は以下の通りです。
- インターネットで〇〇(資格名) 参考書などのキーワードで検索する
- 検索結果から、3つほど記事を読み、内容が理解しやすそうな参考書の目星をつける
- 本屋さんへ行き、②で目星をつけた参考書を実際に見て、選ぶ
参考書を選ぶときに、意識している観点は「覚えやすいレイアウト」と「余白」です。
覚えやすいレイアウトというのは、重要な部分の文字の色であったり、図や表の量です。私の場合は重要な部分は赤色やオレンジ色など暖色系だと赤シートで消すことができ、勉強しやすいので、そういったものを選ぶようにしています。また、図や表が多い方が視覚的に理解できるので、文字ばかりの参考書よりは図などで表現してあるものを選んでいます。
余白というのは、ページ全体に対する文字の量が多すぎないということです。文字の量が多すぎると一気にたくさんの情報を得ることで、覚えにくくなっていると感じてしまいます。そのため、余白は意識しています。
問題集も選び方は参考書と同様です。意識する観点だけ少し異なる部分もあるので、解説します。「覚えやすいレイアウト」と「余白」は同じですが、追加で「解説のわかりやすさ」も問題集では重要になります。
解説のわかりやすさとは、そのままですが、解説がわかりやすく示されているかということです。
例えば、
- 答えの選択肢で出てきた正解とは別の選択肢の解説がのっている
- 解説にも図や表が使われている
- 問題や答えに関連するページ番号が書かれている
などといったものがある場合は、わかりやすいのではないかと思っています。
文字ばかりでよくわからなくなってきたかもしれないので、参考書や問題集を選ぶときに意識することについて整理したものを以下に書いておきますね。
- 覚えやすいレイアウト
- 重要な部分の文字の色、図や表の量
- 余白
- ページ全体に対する文字の量が多すぎない
- 覚えやすいレイアウト
- 重要な部分の文字の色、図や表の量
- 余白
- ページ全体に対する文字の量が多すぎない
- 解説のわかりやすさ
- わかりやすくなる工夫がなされている
参考書を選ぶときに意識したい観点は人それぞれかと思うので、あなたが理解しやすい参考書はどのようなものか考えてみてくださいね😌
勉強するとき
ここからは実際に勉強するときについて解説していきます。
勉強中に意識するべきことはインプットとアウトプットを繰り返し行うことです。
資格試験は、知識をインプットし、その知識を使って、問いに答えるというものです。
インプットを重要視しがちですが、最終的には問いを使って、アウトプットするということなので、正しくアウトプットするということが必要になります。
ここまで抽象的なことばかりでよくわからないとなっているかもしれないので、具体的にいうと、
「参考書でインプットし、問題集でアウトプットをする」←これを何度も繰り返す
ということです。
特に大学生の授業やバイト、部活でいそがしいときには、時間を取るのも難しくなってくるでしょう。(社会人の方で忙しいという方も当てはまりますね。)そんなときはインプットを移動時間やスキマ時間でやるようにしましょう。まとまった時間がなくても、インプットは可能です。スキマ時間でやることで、同じところを目にする回数を多くし、覚えやすくなるというメリットにすることもできます。無理のない範囲で時間を作り出せるといいですね⏰
また、アウトプットの最終段階として、模擬試験を解きましょう。
試験時間と同様の時間で、環境も試験と同じように整えてください。模擬試験は2週間前までには、最低1回実施しましょう。
目的としては、「全体の何割を解くことができるのかを試す」「試験当日に変に緊張しない」ためです。
同じ時間内でどれほど解けるのかを把握することで、当日までの残りの期間でやるべきことを明確化します。もし時間が足りないのであれば、問題を見てから解答するまでを速くするための勉強、わからない問題が多いのであれば、インプットを増やすなどと、自分の課題に対して勉強方法を見極めて実施することができます。
また、当日と同じ環境にすることで、本番での緊張を和らげることができると思います。本番と全く同じ環境や心持ちにすることは難しいかもしれませんが、なるべく近づけることで本番の雰囲気を全く感じていないよりは緊張がほぐれるはずです。緊張でミスをするのを防ぐ効果も期待できるでしょう。
試験日
試験日の試験時間前までにやることは、苦手なところの再確認です。
試験日までにたくさんの知識をインプットし、さまざまな問題を解いていくと思います。その中でこの分野はこの問題がよく出ている、この部分がいつも間違えてしまうなど、試験の傾向と自分の傾向をわかっていると思います。
優先順位をつけて、最後まで諦めずにできることをやりましょう
優先順位は以下の順番だと考えています(①が優先順位1番という意味です。)
- 頻出分野/問題で苦手なところ
- 頻出分野/問題で得意なところ
- 非頻出分野/問題で得意なところ
- 非頻出分野/問題で苦手なところ
頻出分野はあなたが試験を受けるときも出る可能性があるので、優先順位が高めです。また、資格試験は満点を取らないと合格できないわけではないので、非頻出分野で苦手なところよりも取れる可能性のある部分に時間を割いた方が点数が上がる可能性が上がります。
また、試験中はとにかく時間内でより多くの問題を解くことを意識をしましょう。そして、早く終わってしまったら、見直しをしてください。あとで見直すことで、違う解答をしていたり、解答欄がずれているなどというミスに気づくことができます。解答欄がずれていると、多くの点数を取りこぼしてしまうことになるので、避けたいところです。しかし、人間はミスをするので、見直しをして、ミスに気づけるようにしましょう。
おすすめの勉強場所
勉強で意識することがわかったところで、次は「ではどこで勉強するのが効果的か?」ということをお伝えします。
ここでは、おすすめの勉強場所について、解説していきます。
勉強場所は大きく2つに分けられると思います。
- 静かに集中できる場所
- 少し音があるが、日常とは異なる場所で集中できる場所
それぞれでご紹介してきます。
静かに集中できる場所
静かに集中できる場所としては、「自宅」「図書館」をおすすめします。
自宅は、自分自身で静かな環境を作ることができます。また、日常の一部の空間なので、移動がなかったり、自分が集中しやすい好きな空間を作り出すことができます。
しかし、自宅ではスマホがいつでも触れる空間でもあり、1人だと集中できないという人もいます。そんな人におすすめなのが図書館の自習スペースです。図書館は静かに本を読んだり、勉強をする空間になっているので、静かな環境が担保されます。また、他にも自習スペースを使っている人がいたり、スタッフの方がいるので、1人だと集中できないという問題を解消することができます。
少し音があるが、日常とは異なる場所で集中できる場所
少し音があるが、日常とは異なる場所で集中できる場所としては、「カフェ」「コワーキングスペース」をおすすめします。
カフェは、勉強している人も多くいますね。カフェでは、ゆったりとした音楽が流れているので、勉強しやすい空間でもあります。また、1人で本を読んでいたり、勉強していたりと、1人の人も多くいるので、1人であることへの抵抗感も感じにくいと思います。好きなドリンクやフードを勉強のお供とするとモチベーションが上がるという人にはもってこいな場所です。
しかし、話している人も比較的多いので、人の声の量を抑えたいという人には、コワーキングスペースをおすすめします。コワーキングスペースはどこにでもあるという場所ではないですが、駅の近くや比較的都会に近いところにはありますね。ミーティングなどをして、話し声もしますが、カフェほどは話し声が気にならないと思います。
ちなみにわたしは自宅と図書館を使うことが多いです。理由としては、お金がかからないことと、静かな場所であることが挙げれられます。個人的には、勉強の場所としてお金がかからないというのは大きなメリットです。また、あまり音がある環境で勉強をするのが得意ではないので、静かな場所を使っています。気分を変えたいときやモチベーションが上がらないときは新鮮さを感じるためにカフェに行くこともあります😊
自分の集中しやすい勉強場所を探してみてください。
必要なもの
ここでは、資格取得に向けて、必要なものを解説します。
試験日前日まで
試験日前日までに必要なものは以下の6つです。
- 参考書
- 問題集
- ノートや紙
- 筆記用具
- タイマー
- お金
基本的には勉強するために必要なものです。
タイマーに関しては本番と同じ時間内で解く練習をする模擬試験をするときに必要になるため、記載しています。スマホやパソコンでもタイマー機能はありますが、本番は電子機器を使うことができないので、同じ状況を作るため、タイマーを準備しておきましょう。
また、お金に関しては、受験料という意味です。資格によって異なりますが、クレジットカード払い、コンビニ払いなどあるので、自分のやりやすい支払い方法で払ったら良いでしょう。
試験日当日
試験日前日までに必要なものは以下の4つです。
- 参考書
- (もしあれば)内容をまとめたノートや紙
- 筆記用具
- 受験票
- 身分証明書
試験会場へ電車やバスなど、公共交通機関で行く人は車内でも勉強できるので、最終確認をするために必要なものを持っていきましょう。
また、試験日には受験票や身分証明書(必要な場合あり)を必ず持っていきましょう。それがないと受験できない可能性があるので、しっかりと持っているか確認してから受験会場に向かってくださいね。
資格に関するよくある質問
最後に、資格に関する質問について、答えていきます!
受ける資格の選び方は?
わたしは以下の2つのどちらかで選んでいます。
- 今、興味がある資格
- 将来必要になりそうな資格
資格取得の目的にもつながってきますが、資格の範囲を勉強することによって得られること、資格を取得することによって得られることを踏まえて考えています。
また、せっかく勉強するなら、今後の生活や仕事に生かされるものだとモチベーションも上がるので、そういった観点も踏まえています。
大学生が取得するといい資格は?
おすすめは、ITパスポートです。
近年はITの知識が必要とされたり、IT分野に進出している企業もたくさんあります。どんな道に進んだとしても、ITの基礎知識を持っておいて損はないので、おすすめです。
わたしもITパスポートは取得しましたが、幅広い分野を学ぶことができるので、勉強しておくだけでも有益です。
大学生で資格を取得するべき?
専門職でない限り、資格を持っていなければならないということはほとんどありませんが、勉強習慣を継続しておいたり、特定の分野の専門知識をつけるという意味では資格取得を目指しても良いと考えています。
大学生は自分で勉強習慣を作らない限り、習慣がなくなってしまいます。高校生までで定期的に勉強していた時期がなくなると改めて習慣を作るのは時間も労力もかかります。そのため、定期的に資格取得に向けた勉強をすることで、習慣を無理なく継続させることができます。
しかし、ここはあなたが資格取得を目指したいかどうかになるので、やりたいと思った方はぜひ資格取得を目指してみるといいと思います。
取得する資格を決めて、勉強を始めよう。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
この記事を読んでくださっているということは、何か資格を受けてみたいけど、勉強方法が分からなかったり、資格を受けることを迷っている人だと思います。やってみたいという気持ちがあるのであれば、挑戦してみてほしいです。
わたしもやるか迷ったり、やっぱりやらなくてもいいのでは?と思ったときもありましたが、実際に勉強したり、資格を取得したことで得られたこともたくさんあります。
この記事があなたが資格の勉強をするときに少しでも役に立つものであれば幸いです!
無理のない範囲で頑張ってくださいね🔥